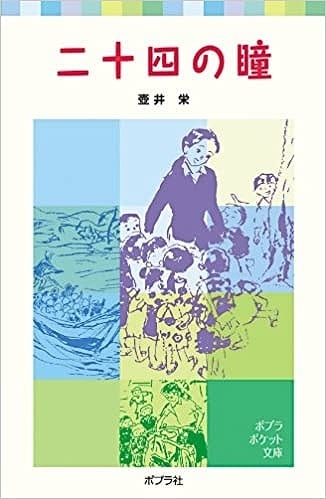近現代のお弁当箱
職場や学校へお弁当持参の習慣が浸透したのは明治時代からです。その頃の持ち運び用の容器は竹皮や柳行李など身近な植物素材のものでした。
やがて機能性が重視されるようになり、1897(明治30)年にアルミニウムの軍用弁当箱が作られます。軽く丈夫で手入れも簡単でしたが、変形や腐食しやすいのが難点でした。昭和年代初めにアルミニウムに酸化被膜を作り強度と耐食性を高める加工をしたアルマイト弁当箱が登場します。着色性に優れ、お弁当箱にきれいな色の図柄をつけることができました。壷井栄の小説『二十四の瞳』(1952)に百合の花の絵がついたアルマイトのお弁当箱にあこがれる少女が出てきます。銀色に輝き美しい絵がついたお弁当箱は人々の羨望の的でした。
1960年代半ばに魔法瓶の構造を応用した保温弁当箱が登場します。「温かいお弁当を食べたい」という思いに応えるものです。今はさらに素材も形状も多様化し、カラフルでおしゃれなお弁当箱がたくさんあります。小さなお弁当箱にも時代の社会状況や人々の思いが反映されています。
監修・解説:権代美重子(食文化研究家)
戦後の日本の復興のために働いた日雇土木労働者の空腹を満たした厚さ5cmほどの深型弁当箱。「ドカベン(土方弁当)」と呼ばれ、ぎっしり詰まったご飯の上に梅干し(「日の丸弁当」)が定番であった。アルミニウムで塩分によって腐食しやすく、蓋の梅干しが接する部分に穴があいた。アルマイトは1941年発令の金属類回収令によって供出の対象になり、戦後もしばらく姿を消していた。
ご飯の中央に副食として梅干し1個だけを乗せたもので、日本の国旗(日の丸)のデザインに似ていることが名の由来である。戦時中、戦意高揚のため興亜奉公日の食事に奨励された。シンプルだが、梅干しのアルカリが米の酸性を中和し、米のカロリーが食べてすぐエネルギーに変わる。また、梅干しには疲労回復効果の他に殺菌効果や解毒効果もあり、優れた労働食といえる。
1950年代に汁もれ防止のゴム製パッキンつきのおかず入れが登場する。蓋のずれを防止する留め具もついている。「モダン菜入れ」「安全菜入れ」などと呼ばれた。
ブック型弁当
1970年に中学生向きにおかず用の仕切りをつけ蓋に箸入れを装着したブック型弁当箱が登場する。それまでの弁当箱はかさばってカバンと別にもっていかなければならなかったが、教科書とともにカバンに入れられるようになり、百貨店に行列ができるほど大ヒットする。これは発売初期のもので、よく使いこまれていることから愛用されていたことがわかる。
キャラクターアルティマイト弁当
アルマイト弁当箱の蓋に様々なオフセット印刷された「絵付き弁当箱」は大人気で、発売されるや市場を席捲し圧倒的シェアを占めるようになる。小説『二十四の瞳』に登場する少女は花柄の弁当箱にあこがれたが、現代ではアニメの主人公他さまざまなキャラクターを印刷したお弁当箱があり、子供たちに変わらぬ人気がある。
1970年代登場のステンレス製の真空断熱構造保温機能付弁当箱。機能は保温50度以上、保冷15度以下が多く、オールシーズン使用できる。用途に応じて重量や容量の異なる種類がある。定番は容器を3つ重ねたもので、一番下に味噌汁、二段目にご飯、三段目におかずを入れることができ、一番下に入れた味噌汁の熱によって、二段目のご飯を温めるようになっている。弁当を単なる携行食から、「温かい 汁、おかず、ご飯とそろった楽しむ食事」へと進化させた。
1990年代後期発売のシチュー、カレー、みそ汁などのスープ類が保温携帯できる魔法瓶。断熱効果が高く、約カップ3杯分の量が60℃前後で約6時間保温できる。むろん、保冷も可能。朝用意して昼食に弁当として食べること、一般的な場所で使用することを考慮し携帯しやすいよう作られている。内容器には抗菌加工がされており、電子レンジにも対応できる。便利さからスープ弁当ブームが起こる。
1975年(昭和50年)登場。コンセントで電源につなぎ温める仕組みの初期の電気弁当箱。3時間ほどでご飯は温まるが、おかずは温まらなかった。かさばる上に電源が必要なのでどこでも使用できるわけではなく非実用的で、これは普及しなかった。
小説『二十四の瞳』と「百合の花のお弁当箱」
『二十四の瞳」は、瀬戸内海べりの一寒村を舞台に小学校の新米女性教師大石先生と12人の生徒のふれあいを描いた物語です。時代は昭和3年から戦後昭和21年まで。
分教場の生徒たちは5年生になるとお弁当をもって本校に通います。その頃、アルマイトのお弁当箱が登場し人気でした。 村でも何人かの少女が蓋に百合の花の絵がついたアルマイトのお弁当箱を買ってもらっていました。生徒の一人松江も、それを見てほしくてたまりません。家の貧乏は承知で母親にねだりますが、用意してくれたのは古い柳行李の弁当箱。あきらめきれない松江は泣いてねだります。気持ちを察した母親は「子供が生まれて起きられるようになったら買ってあげる」と約束します。早産で女の子が生まれ、松江はもうすぐ百合の花のお弁当箱を買ってもらえると嬉しくてたまりません。初登校の日、大石先生にそのことを話します。けれど、その日母親はお産の無理がたたり亡くなります。赤ん坊の世話と家事が松江の仕事になりました。
その後ずっと学校を休んでいる松江のことが気になって、大石先生は百合の花の弁当箱をもって家を訪ねます。「学校に来れるようになったら使ってね」との言葉もむなしく、松江は奉公に出されることになります。松江が登校したのは、あの日1日だけ、もうお弁当箱を使う機会はありません。
時は流れて戦後、結婚して離職していた大石先生が復職することになり、教え子たちが歓迎会を企画します。母になった松江が、あのお弁当箱をもって参加します。松江は戦争中、防空壕の中にも持って入りました。一度も使うことはなかったけれど、11歳で家を離れ奉公に出た松江にとって、「百合の花のお弁当箱」は心の支えであり大切な宝ものでした。